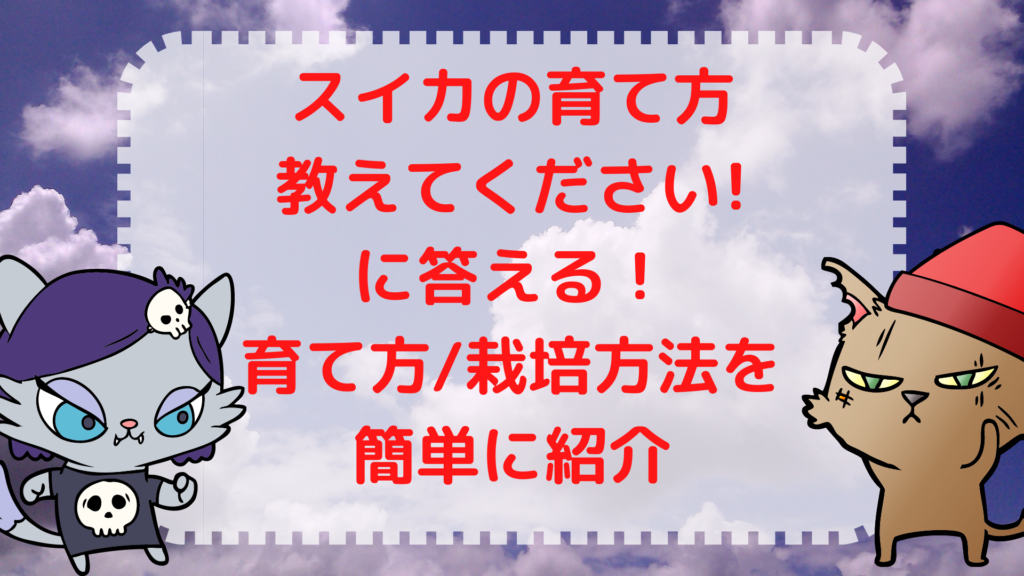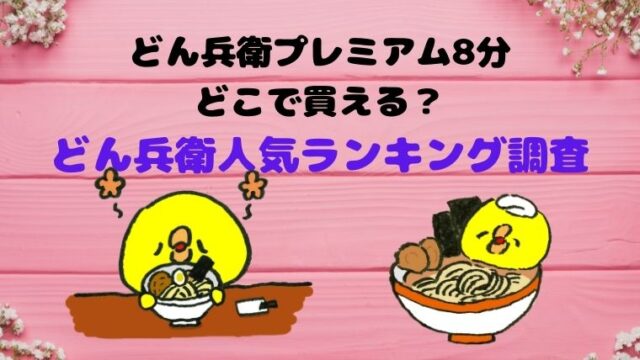日本の夏の風物詩の1つとしてあげられるのが「スイカ」。
お好きな方も多いのではないでしょうか?甘みがあって水分をたっぷり含んだスイカは、暑い夏のデザートにもぴったりですよね。
美味しいスイカを自分でも作ってみたい!と思う方もいらっしゃると思います。
ですが、家庭でのスイカ栽培はとても難しそうなイメージがありますよね。
そこで今回は、初心者でも出来る!栽培が難しいと言われるスイカの基本的な栽培方法や適した環境づくり、
収穫までのお手入れのやり方などをご紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
パッと読める目次
スイカの育て方で注意しないといけないこと

美味しいスイカを家庭で育てるにはいくつか注意点があります。
生育に適した環境の作り方や害虫被害などをお伝えしていきます。
栽培環境(日当たり・置き場所)
スイカを地這いで育てる場合はスペースが必要です。
スイカはツルがとても大きく伸びるので、広い面積が必要になります。
地這いでの栽培が好ましいですが、大型のプランターでの栽培も可能です。
また、プランターではなく植木鉢でも育てることができます。
大事なのは、大型のものを選び、のびのびとした環境で育ててあげることです。
ゆとりを持った環境づくりをしましょう。
また、日当たりにも注意が必要です。
強い日光を好むので日当たりの良い場所を選びましょう。
また、スイカは乾燥した場所を好むため、風通しの良いところで育てるようにしましょう。
ベランダで育てている場合は、柵の前などに置いてあげると良いかもしれません。
温度
スイカの生育に適した温度は23~30度です。
13度を下回ると生育が止まってしまいますし、だからといって40度以上の環境に何日も置いておくとうまく育ってくれません。
日光には充分当てるが、高温になりすぎないように適温を守るように気をつけましょう。
用土
スイカは一つ一つが大きく育つので、1株あたり80センチ程度の株間隔が必要になります。
それを見越して植え付ける場所を選びましょう。
スイカは酸性の土壌を好みません。
植え付け2週間前には、堆肥(たいひ)と苦土石灰を土にまいてよく耕しましょう。
堆肥は1平方キロメートルあたり2キロ、苦土石灰は1平方キロメートルあたり150グラムです。
その後1週間前には元肥に化成肥料を30グラム混ぜて畝を立てておきましょう。
水のやりすぎ注意
スイカは多湿を嫌う性質を持っているため、水やりをあまり必要としません。
過剰に水をあげてしまうと、水っぽい味のスイカになってしまいます。
水を与えすぎない状況を作ることができれば、糖度が高くなります。
夏になると朝夕に1回ずつ水をあげる必要もありますが、
基本的に土の表面が乾いたタイミングで水を与えるようにしましょう。
スポンサーリンク
肥料のタイミング
肥料のあげすぎにも注意が必要です。
肥料を与えすぎると根の水分がうばわれ痛みだし、結果的に肥料やけを起こします。
肥料をやりすぎて実が付かない現象=つるぼけ状態になると、
栄養分がツルや葉の成長に流れてしまい、花が咲かなくなったり、実がならなくなったりします。
「大きく育って欲しい!」という思いからたくさんの肥料をあげがちですが、結果的に成長を妨げてしまう恐れがあるので注意しましょう。
病中虫
スイカの栽培には気をつけてあげないといけない病中虫も存在します。
意外と知らなかった!なにそんな虫いるの?
病中虫がいたらどうなるの?そんな疑問にお答えします。
<アブラムシ>
アブラムシは体長3ミリ以下の虫で、葉や茎に大量に発生し、葉や茎を吸汁します。
大量に発生してしまった株は生育が阻害され、アブラムシの排泄物にカビが発生し「すす病」を発病します。
新葉に発生することが多く、ツルの伸長も止まってしまう恐れがあります。
予防策としては、マルチを敷くと成虫の飛来を防ぐことができます。
<ハダニ>
ハダニは体長1ミリほどの小ささで、目視で見つけることはとても難しいです。
葉の裏にくっついて吸汁しながら繁殖します。
ハダニが吸汁した後の葉は、葉緑素が抜けて白く見えるようになります。
やがてその部分が枯死して黒くなり、 より被害が広がると、光合成が行えなくなり葉が枯死してしまう恐れがあります。
高温、乾燥した環境を好みますので、予防策としては時々霧吹きなどで葉に水を与えると良いです。
<ウリハムシ>
ウリハムシは体長7~8ミリほどです。スイカのあちこちにいることもあり、成虫・幼虫ともに葉や根を食害します。
被害が多発すると、葉が食い荒らされて丸い穴が開いたり、線が入ってしまいます。
葉をよくチェックして、成虫がいたらすぐに捕殺するようにしましょう。
気温が低い午前中の早い時間帯であれば、ウリハムシの動きも鈍く捕獲しやすいかと思います。
害虫はどこからともなく飛来し、気が付かないうちに繁殖してしまう恐れがあるので注意が必要です。
葉や茎などをよく観察し、見つけ次第捕殺しましょう。
早期発見をすることで、被害を最小限に抑えることが可能です。
スポンサーリンク
スイカの育て方・栽培方法

次に、スイカの栽培に適した時期や作業のやり方をご紹介します。
育て方(種まき編)
種まきの適期は3月~4月です。これより早い時期だと種が凍ってしまうし、
遅いと生育が遅れてしまい、収穫に間に合わなくなってしまうで適期は守るようにしましょう。
種から育てる場合は育苗ポットを利用します。
ひとつのポットに3粒~4粒まき、厚さ1センチ程の土をかぶせて平らにします。
そこにたっぷりの水をあげて、25度~30度の環境を保ちながら管理しましょう。
うまくいけば4日ほどで発芽します。
発芽したら育ちの良い本葉を1つだけ残し、あとは間引きします。
発芽して間もない芽はとてもデリケートです。ていねいに優しく行うようにしましょう。
そして種まきから約30日後、本葉が4~5枚になったのを確認できたら定植しましょう。
ちなみに、スイカは苗から育てるほうが手軽です。5月頃には苗が流通し始めるので、育苗が難しい場合はそちらを試してみるのも良いかもしれません。
育て方・(植え付け)
植え付けの適期は5月中旬~6月中旬です。日当たり、風通しの良いところに植え付けましょう。
根鉢が崩れてしまうと根を痛めてしまう恐れがあります。
根鉢を崩さないようにポットから取り出し、優しく丁寧に植え付けましょう。
植え付けの後もたっぷりと水を与え、しっかりと根が張るまでは保温してあげるのが大切です。
そうすることにより生育がより良くなります。
育て方(摘芯(摘心))
スイカは子づるに実をつけます。
本葉が5~6枚ほどになった時に、成長している親づるの先端の部分を摘み取り成長を止めます。
この作業を「摘芯(摘心)」と言います。 親づるを摘芯すると子づるの成長が促進されます。
ですが子づるの増えすぎも良くないため、元気に育っている2~3本を残し他は摘み取りましょう。
スイカの収穫はこのタイミング!

スイカの収穫の適期は7月中旬~8月下旬です。
雄花と雌花が咲いたら、雄花を摘み取って雌花に擦り付けて受粉させる「人工授粉」から大体40日程度です。
品質によりますが、受粉からの日数で判断します。なので受粉した日を忘れないようにしましょう。
ツルに近い上の方を手のひらで叩くと低くて鈍い音がすれば適期です。
まだ時期が早い場合はコンコンと高い音がします。また巻きひげが枯れたり、葉が黄色くなっていることも
収穫の目安になります。
収穫の仕方ですが、つるの部分をハサミで切ります。
スイカのつるは太いため、よく切れる園芸用のハサミを準備しておきましょう。
スイカの収穫時期の判断はとても難しいです。
収穫に踏み切る前に、試し割りをして状態を確かめてみるのも良いかもしれません。
まとめ

スイカの栽培方法をご紹介しました。
スイカはとてもデリケートです。初心者の方は種からの栽培ではなく、苗からであれば上手に育てることが出来るのでおすすめです。
害虫をこまめに取ったり、スイカ全体をまんべんなく日光に当ててあげたりと手がかかります。
ですが頻繁に様子を見てケアをしてあげて、適した環境でしっかりと管理できれば難しくはありません。
自分で手間ひまかけて、愛情込めて作ったスイカの美味しさは格別です。
ぜひ、スイカ栽培にチャレンジしてみてくださいね。
スポンサーリンク